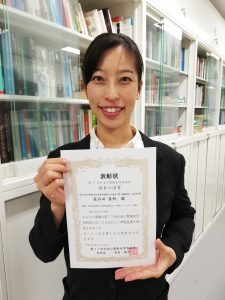2019年1月22日
児童虐待のいたましいニュースが最近目立つようになり、社会的関心も高まってきましたが、 個別事例の断片的な情報が横行し、児童虐待の実態や問題点を明らかにするようなデータが日本では不足しています。
一方、米国では、児童虐待に関する全国統計が1990年 代から構築され、政策効果を実証研究を通じて明らかにする様々な試みが進められています。児童虐待の実証研究で若手第一人者の一人、オハイオ州立大学のJohnson-Motoyama先生をお招きして、米国の現状、エビデンスに基づく児童虐待対策を構築するうえで克服すべき課題などについて講義していただきました。参加者と大変熱のこもった議論が展開されました。